大本教の聖師として20世紀前半活躍した出口王仁三郎は、出色した霊能者であり予言者であり宗教家であった。太平洋戦争の勃発と敗戦を予言していたことでも知られる。その功績は、未だ世界からほとんど評価されていない。あまりにも巨人であるがために理解できないようである。しかし、王仁三郎が主張し記述した内容は神からのメッセージであり真理である。これから研究を深めていくことが必要である。神のメッセージが隠されているのである。
今回、王仁三郎が芙蓉仙人に先導されて訪れた霊界の入り口と審判について紹介する。ここで紹介する内容は、霊界物語.ネット~出口王仁三郎大図書館~からの転載であることをお断りしておく。
https://reikaimonogatari.net/index.php?obc=rm0105
霊界の姿―天界、地獄界の様子については、上記WEBサイトに詳しく記述紹介されているので、関心のある方はアクセスしてください。
霊界物語 > 第1巻 > 第1篇 幽界の探険 > 第5章 霊界の修業
霊界には天界と、地獄界と、中有界との三大境域があつて、天界は正しき神々や正しき人々の霊魂の安住する国であり、地獄界は邪神の集まる国であり、罪悪者の堕ちてゆく国である。そして天界は至善、至美、至明、至楽の神境で、天の神界、地の神界に別れてをり、天の神界にも地の神界にも、各自三段の区劃が定まり、上中下の三段の御魂が、それぞれに鎮まる楽園である。地獄界も根の国、底の国にわかれ、各自三段に区劃され、罪の軽重、大小によりて、それぞれに堕ちてゆく至悪、至醜、至寒、至苦の刑域である。今自分はここに霊界の御許しを得て、天界、地獄界などの大要を表示して見やう。
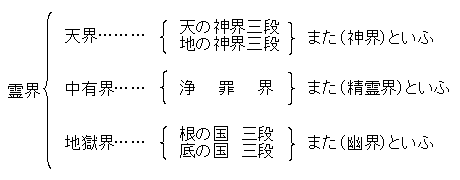
[#図 霊界の大要]
霊界の大要は大略前記のとほりであるが、自分は芙蓉仙人の先導にて、霊界探険の途に上ることとなつた。勿論身は高熊山に端坐して、ただ霊魂のみが往つたのである。
行くこと数百千里、空中飛行船以上の大速力で、足も地につかず、ほとんど十分ばかり進行をつづけたと思ふと、たちまち芙蓉仙人は立留まつて自分を顧み、
『いよいよ是からが霊界の関門である』
といつて、大変な大きな河の辺に立つた。一寸見たところでは非常に深いやうであるが、渡つて見ると余り深くはない。不思議にも自分の着てゐた紺衣は、水に洗はれたのか忽ち純白に変じた。別に衣服の一端をも水に浸したとも思はぬに、肩先まで全部が清白になつた。芙蓉仙人とともに、名も知らぬこの大河を対岸へ渡りきり、水瀬を眺めると不思議にも水の流れと思つたのは誤りか、大蛇が幾百万とも限りなきほど集まつて、各自に頭をもたげ、火焔の舌を吐いてをるのには驚かされた。それから次々に渉りきたる数多の旅人らしきものが、いづれも皆大河と思つたと見えて、自分の渉つたやうに、各自に裾を捲きあげてをる。そして不思議なことには各自の衣服が種々の色に変化することであつた。あるひは黒に、あるひは黄色に茶褐色に、その他雑多の色に忽然として変つてくるのを、どこともなく、五六人の恐い顔をした男が一々姓名を呼びとめて、一人々々に切符のやうなものをその衣服につけてやる。そして速く立てよと促す。旅人は各自に前方に向つて歩を進め、一里ばかりも進んだと思ふ所に、一つの役所のやうなものが建つてあつた。その中から四五の番卒が現はれて、その切符を剥ぎとり、衣服の変色の模様によつて、上衣を一枚脱ぎとるもあり、或ひは二枚にしられるもあり、丸裸にしられるのもある。また一枚も脱ぎとらずに、他の旅人から取つた衣物を、或ひは一枚あるいは二枚三枚、中には七八枚も被せられて苦しさうにして出てゆくものもある。一人々々に番卒が附き添ひ、各自規定の場所へ送られて行くのを見た。
霊界物語 > 第1巻 > 第1篇 幽界の探険 > 第6章 八衢の光
ここは黄泉の八衢といふ所で米の字形の辻である。その真中に一つの霊界の政庁があつて、牛頭馬頭の恐い番卒が、猛獣の皮衣を身につけたのもあり、丸裸に猛獣の皮の褌を締めこみ、突棒や、手槍や、鋸や、斧、鉄棒に、長い火箸などを携へた奴が沢山に出てくる。自分は芙蓉仙人の案内で、ズツト奥へ通ると、その中の小頭ともいふやうな鬼面の男が、長剣を杖に突きながら出迎へた。そして芙蓉仙人に向つて、
『御遠方の所はるばる御苦労でした。今日は何の御用にて御来幽になりましたか』
と恐い顔に似合はぬ慇懃な挨拶をしてゐる。自分は意外の感にうたれて、両者の応答を聞くのみであつた。芙蓉仙人は一礼を報いながら、
『大神の命により大切なる修業者を案内申して参りました。すなはちこの精霊でありますが、今回は現、神、幽の三界的使命を帯び、第一に幽界の視察を兼ねて修業にきたのです。この精霊は丹州高倉山に古来秘めおかれました、三つ葉躑躅の霊魂です。何とぞ大王にこの旨御伝達をねがひます』
と、言葉に力をこめての依頼であつた。小頭は仙人に軽く一礼して急ぎ奥に行つた。待つことやや少時、奥には何事の起りしかと思はるるばかりの物音が聞ゆる。芙蓉仙人に、
『あの物音は何でせうか』
と尋ねてみた。仙人はただちに、
『修業者の来幽につき準備せむがためである』
と答へられた。自分は怪しみて、
『修業者とは誰ですか』
と問ふ。仙人は答へていふ、
『汝のことだ。肉体ある精霊、幽界に来るときは、いつも庁内の模様を一時変更さるる定めである。今日は別けて、神界より前もつて沙汰なかりし故に、幽庁では、狼狽の体と見える』
と仰せられた。しばらくありて静かに隔ての戸を開いて、前の小頭は先導に立ち、数名の守卒らしきものと共に出できたり、軽く二人に目礼し前後に付添うて、奥へ奥へと導きゆく。上段の間には白髪異様の老神が、机を前におき端座したまふ。何となく威厳があり且つ優しみがある。そしてきはめて美しい面貌であつた。
芙蓉仙人は少しく腰を屈めながら、その右前側に坐して何事か奏上する様子である。判神は綺羅星のごとくに中段の間に列んでゐた。老神は自分を見て美はしき慈光をたたへ笑顔を作りながら、
『修業者殿、遠方大儀である。はやく是に』
と老神の左前側に自分を着座しめられた。老神と芙蓉仙人と自分とは、三角形の陣をとつた。自分は座につき老神に向つて低頭平身敬意を表した。老神もまた同じく敬意を表して頓首したまひ、
『吾は根の国底の国の監督を天神より命ぜられ、三千有余年当庁に主たり、大王たり。今や天運循環、いよいよわが任務は一年余にして終る。余は汝とともに霊界、現界において相提携して、以て宇宙の大神業に参加せむ。しかしながら吾はすでに永年幽界を主宰したれば今さら幽界を探究するの要なし。汝は今はじめての来幽なれば、現幽両界のため、実地について研究さるるの要あり。しからざれば今後において、三界を救ふべき大慈の神人たることを得ざるべし。是非々々根の国、底の国を探究の上帰顕あれよ。汝の産土の神を招き奉らむ』
とて、天の石笛の音もさはやかに吹きたてたまへば、忽然として白衣の神姿、雲に乗りて降りたまひ、三者の前に現はれ、叮重なる態度をもつて、何事か小声に大王に詔らせたまひ、つぎに幽庁列座の神にむかひ厚く礼を述べ、つぎに芙蓉仙人に対して、氏子を御世話であつたと感謝され、最後に自分にむかつて一巻の書を授けたまひ、頭上より神息を吹きこみたまふや、自分の腹部ことに臍下丹田は、にはかに暖か味を感じ、身魂の全部に無限無量の力を与へられたやうに覚えた。
霊界物語 > 第1巻 > 第1篇 幽界の探険 > 第7章 幽庁の審判
ここに大王の聴許をえて、自分は産土神、芙蓉仙人とともに審判廷の傍聴をなすことを得た。仰ぎ見るばかりの高座には大王出御あり、二三尺下の座には、形相すさまじき冥官らが列座してゐる。最下の審判廷には数多の者が土下座になつて畏まつてゐる。見わたせば自分につづいて大蛇の川をわたつてきた旅人も、早すでに多数の者の中に混じりこんで審判の言ひ渡しを待つてゐる。日本人ばかりかと思へば、支那人、朝鮮人、西洋人なぞも沢山にゐるのを見た。自分はある川柳に、
『唐人を入り込みにせぬ地獄の絵』
といふのがある、それを思ひだして、この光景を怪しみ、仙人に耳語してその故を尋ねた。何と思つたか、仙人は頭を左右に振つたきり、一言も答へてくれぬ。自分も強て尋ねることを控へた。
ふと大王の容貌を見ると、アツと驚いて倒れむばかりになつた。そこを産土の神と仙人とが左右から支へて下さつた。もしこのときに二柱の御介抱がなかつたら、自分は気絶したかも知れぬ。今まで温和優美にして犯すべからざる威厳を具へ、美はしき無限の笑をたたへたまひし大王の形相は、たちまち真紅と変じ、眼は非常に巨大に、口は耳のあたりまで引裂け、口内より火焔の舌を吐きたまふ。冥官また同じく形相すさまじく、面をあげて見る能はず、審判廷はにはかに物凄さを増してきた。
大王は中段に坐せる冥官の一人を手招きしたまへば、冥官かしこまりて御前に出づ。大王は冥官に一巻の書帳を授けたまへば、冥官うやうやしく押いただき元の座に帰りて、一々罪人の姓名を呼びて判決文を朗読するのである。番卒は順次に呼ばれたる罪人を引きたてて幽廷を退く。現界の裁判のごとく予審だの、控訴だの、大審院だのといふやうな設備もなければ、弁護人もなく、単に判決の言ひ渡しのみで、きはめて簡単である。自分は仙人を顧みて、
『何ゆゑに冥界の審判は斯くのごとく簡単なりや』
と尋ねた。仙人は答へて、
『人間界の裁判は常に誤判がある。人間は形の見へぬものには一切駄目である。ゆゑに幾度も慎重に審査せなくてはならぬが、冥界の審判は三世洞察自在の神の審判なれば、何ほど簡単であつても毫末も過誤はない。また罪の軽重大小は、大蛇川を渡るとき着衣の変色によりて明白に判ずるをもつて、ふたたび審判の必要は絶無なり』
と教へられた。一順言ひ渡しがすむと、大王はしづかに座を立ちて、元の御居間に帰られた。自分もまた再び大王の御前に招ぜられ、恐る恐る顔を上げると、コハそもいかに、今までの恐ろしき形相は跡形もなく変らせたまひて、また元の温和にして慈愛に富める、美はしき御面貌に返つてをられた。神諭に、
『因縁ありて、昔から鬼神と言はれた、艮の金神のそのままの御魂であるから、改心のできた、誠の人民が前へ参りたら、結構な、いふに言はれぬ、優しき神であれども、ちよつとでも、心に身欲がありたり、慢神いたしたり、思惑がありたり、神に敵対心のある人民が、傍へ出て参りたら、すぐに相好は変りて、鬼か、大蛇のやうになる恐い身魂であるぞよ』
と示されてあるのを初めて拝したときは、どうしても、今度の冥界にきたりて大王に対面したときの光景を、思ひ出さずにはをられなかつた。また教祖をはじめて拝顔したときに、その優美にして温和、かつ慈愛に富める御面貌を見て、大王の御顔を思ひ出さずにはをられなかつた。
大王は座より立つて自分の手を堅く握りながら、両眼に涙をたたへて、
『三葉殿御苦労なれど、これから冥界の修業の実行をはじめられよ。顕幽両界のメシヤたるものは、メシヤの実学を習つておかねばならぬ。湯なりと進ぜたいは山々なれど、湯も水も修行中には禁制である。さて一時も早く実習にかかられよ』
と御声さへも湿らせたまふた。ここで産土の神は大王に、
『何分よろしく御頼み申し上げます』
と仰せられたまま、後をもむかず再び高き雲に乗りて、いづれへか帰つてゆかれた。
仙人もまた大王に黙礼して、自分には何も言はず早々に退座せられた。跡に取りのこされた自分は少しく狼狽の体であつた。大王の御面相は、俄然一変してその眼は鏡のごとく光り輝き、口は耳まで裂け、ふたたび面を向けることができぬほどの恐ろしさ。そこへ先ほどの冥官が番卒を引連れ来たり、たちまち自分の白衣を脱がせ、灰色の衣服に着替させ、第一の門から突き出してしまつた。
突き出されて四辺を見れば、一筋の汚い細い道路に枯草が塞がり、その枯草が皆氷の針のやうになつてゐる。後へも帰れず、進むこともできず、横へゆかうと思へば、深い広い溝が掘つてあり、その溝の中には、恐ろしい厭らしい虫が充満してゐる。自分は進みかね、思案にくれてゐると、空には真黒な怪しい雲が現はれ、雲の間から恐ろしい鬼のやうな物が睨みつめてゐる。後からは恐い顔した柿色の法被を着た冥卒が、穂先の十字形をなした鋭利な槍をもつて突き刺さうとする。止むをえず逃げるやうにして進みゆく。
四五丁ばかり往つた処に、橋のない深い広い川がある。何心なく覗いてみると、何人とも見分けはつかぬが、汚い血とも膿ともわからぬ水に落ちて、身体中を蛭が集つて空身の無い所まで血を吸うてゐる。旅人は苦さうな悲しさうな声でヒシつてゐる。自分もこの溝を越えねばならぬが、翼なき身は如何にして此の広い深い溝が飛び越えられやうか。後からは赤い顔した番卒が、鬼の相好に化つて鋭利の槍をもつて突刺さうとして追ひかけてくる。進退これきはまつて、泣くにも泣けず煩悶してをつた。にはかに思ひ出したのは、先ほど産土の神から授かつた一巻の書である。懐中より取出し押しいただき披いて見ると、畏くも『天照大神、惟神霊幸倍坐世』と筆蹟、墨色ともに、美はしく鮮かに認めてある。自分は思はず知らず『天照大神、惟神霊幸倍坐世』と唱へたとたんに、身は溝の向ふへ渡つてをつた。
番卒はスゴスゴと元の途へ帰つてゆく。まづ一安心して歩を進めると、にはかに寒気酷烈になり、手足が凍えてどうすることも出来ぬ。かかるところへ現はれたのは黄金色の光であつた。ハツと思つて自分が驚いて見てゐるまに、光の玉が脚下二三尺の所に、忽然として降つてきた。
この後、地獄界、天界の訪問記が記述されている。